|
睦言
空が高い―――
夕方のラッシュにはまだ少し早い、どこかのんびりとした駅の階段を降りながら、頼久は襟元に指をねじこむようにして隙間を作った。ネクタイをきつく締め上げた首は薄っすらと汗ばんでいる。
だが、改札を抜けて見上げた空は高く、やはり、もう、秋なのだと思う。
今の仕事を始めてから、こんなに早い時間に帰ることなど一度もなかった。
多分……あかねはまだ帰っていないだろう。
頼久は、まだ暮れもしない町を、いつも通り寄り道ひとつせずにアパートへと向かった。
錆びの付いた郵便受けがギーっという嫌な音を立てる。中には数枚のチラシが投げ込まれていた。
一階の右の端の部屋は、今年の春に空家になってから、今もまだ新しい住人がいないようだ。ぎゅうぎゅうに詰め込まれたチラシの上に更にそれは押し込まれアッカンベーとはみ出している。頼久はそれを一瞥すると、階段脇のはみ出した自転車を一台ずつ真っ直ぐに並べ直し、ふう、と一息つくと、やはり錆び付いて茶色く変色した階段を上がった。
階段を上がった二階の一番奥が、頼久とあかねの暮らす部屋だった。
玄関を入るとすぐに台所、コンロの後ろ側に、お風呂とトイレが並び、洗面所はない。あとは和室が一部屋あるだけの小さな部屋だが、押入れが一間半あることと、角部屋のため台所に小さな窓が付いており、そこから隣に建つ大家さんの自慢の庭が見えることが二人とも気に入っていた。
「ん?」
玄関を開けた瞬間に、頼久は首をかしげる。
部屋が明らかに違っていた。
確かにいつもならば「おかえりなさい」というあかねの声がする。嫌でも目に入る台所のコンロの上には何かしら鍋が乗っており、そこから立ち上る湯気から美味しそうな匂いが漂っていた。時には煮物の甘辛い匂いが、時にはご飯の蒸れた匂いが。そして、そこにはいつもあかねの笑顔があった。
今日はその全てが無い。全てが違う。部屋に入って頼久の目に飛び込んだのは、カーテンを開けっ放しにした窓から見える、まだ明るい空の色だった。
靴を脱ぎ、部屋に上がる。渡す相手がいないから、鞄は足元に置いてしまった。
水道の蛇口を捻り、水をコップに並々と注ぐ。しばらく使っていない時は、少し出しっぱなしにしてからじゃなきゃ駄目だよと、何度もあかねに注意されるのだが、頼久はどうしてもそれができなかった。少しのためらいの後、一気に水を飲み干すと、もう一度コップに水を満たして、今度は口をつけずに奥の部屋へ行き、窓の傍に座りこんだ。
コップを手に持ちながら、自分ひとりしかいない部屋を見渡して、頼久は納得したように小さく笑った。
「ああ……あなたが言っていたのは、このことなのですね」
以前、この部屋に二人で暮らし始めてすぐの頃、あかねがよく言っていたことがある。
『頼久さんの匂いがする』
部屋に一人でいる時に、頼久の匂いがするのだと、あかねが言った時、頼久はそれがよくわからなかった。
『私の匂いですか?』
『うん、たまにね、ふっとくるんだ。そういう時、頼久さんだなーって思う』
『たまに……ふっと……ですか……』
自分の匂い?風呂には毎日入っているが……
『あ、違う違う!!臭いとか言ってるんじゃないんだから嗅がないでよー』
『え?違うのですか?』
腑に落ちない顔をしながら自らの腕に鼻を寄せ、くんくんと匂いを嗅ぎ出した頼久に、あかねは『そういうことじゃないんだなあ』と可笑しそうに笑った。
「あかね……っ、今、あなたの匂いがします」
思わず涙ぐみそうになり、頼久はぎゅっと唇を噛む。
その顔が窓ガラスに映っているのを見て、頼久は焦り、口を開こうとするが、すぐにまた強く噛み締めてしまう。
普段からの癖なのだ。
何かあるたびに、言葉にできずに、すぐに唇を噛む。
そんな自分を歯痒く感じる。
『どうしたの?何か怒ってる?』
今にも、あかねの声が聞こえてきそうだった。
怒ってなどいない、ただ困ってしまうだけだ。
今も、いつも。
ただ、あなたを愛しいと、そう思う気持ちばかり大きくて
自分があなたに何をしてあげられるのか
とにかく不器用で、ただドキドキと嬉しいばかりで
あなたを守るために、この世界で何を……
けれどあなた以上の何もいらない、この幸せに
ただ、困ってしまうだけなのだ……いつも……
そして、今も
あなたの匂いに……
一緒に暮らし、同じ物を使いながら
……何処にでもある安価な物ばかりなのに、あなたはどうしてそんな良い匂いを……
知らない匂いが、今は、なくてはならない匂いになっていて、あなたに会いたくて、あなたをこの腕に抱きしめたくて、あなたに全身包まれたくて……ただ、困ってしまうだけなのです。
あなたがいない、ただそれだけで、こんなにも困ってしまうだなんて、あなたはきっと笑うでしょう。
けれど、それは違う。
あなたはここにいないのに、まるで自然に存在するもののように、ここにいる。
手を伸ばせば、そこに、まあるい温もりを抱きしめられそうなほどに。
だから困ってしまうのです。
頼久は窓を開け、空を見上げた。
きっと、もうすぐ帰ってくるだろうあかねに笑われないように、大きく深呼吸をすると体を伸ばす。
……風呂くらいは沸かしておくべきだろうか。
こんなことを考えるようになった自分は、やはりこの世界に来て変わったのだと思う。
けれど、相変わらず空だけは高く、部屋はあかねの匂いが、ちゃんとあった。
目を閉じても、ほら、ちゃんと、ここに。
| ――おわり |
|
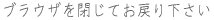
|
|
|
|