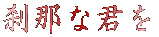
| |
――結局、今宵もこうなってしまったか……
友雅はいささか、自嘲気味につぶやいた。
あかねは小さな寝息をたて彼の腕の中で、あどけない顔で眠っている。
「私は姫にいけないことをしているのか……」
これは、あかねを抱くようになってから幾度となく自身に問い掛けた言葉。しかし、あかねを目の前にすると、そんなことは愚問とばかりに彼女を求めてしまう。
つい先刻もそうだった・・・。
「神子殿」
「友雅さん!こんな時間に困ります……」
「今は誰もいないのだろう?」
「でも……藤姫が……」
「ただ、お話をするだけさ。それだけ。」
友雅はあかねの返事を聞く前に部屋へ入ってきた。
あかねが困っているのは無理もない、まだ夕刻前、藤姫も女御もみな揃っている。
この自室にだって、いつ誰が来るのかしれないのだ。
「友雅さん、どうしたんですか?」
あかねは、急に訪ねてきた友雅の真意がはかりかねた。
普段の彼であれば、用意周到、誰にもわからないようにあかねを誘い出してくれる。
「かわいい顔を見に来ただけだよ。ただ・・・それだけさ」
「また、そんなことばっかり」
「本当だよ。神子殿は最近、つれないからね。今日だって泰明とは出かけたのだろう?」
「そ、そんなことないです。ただ……泰明さんの力を借りたかっただけで」
あかねの困ったような顔に友雅の男が刺激される。
友雅は本当にあかねの顔を見に来ただけだった。いや、少なくとも顔を見るまではそう思っていた。
しかし、実際にあかねに会い、泰明の話をされると妙に苛立つ自分を押さえられなかった。
「神子殿……いや、あかね」
あかねを背後から抱き寄せ、その白いうなじに唇を寄せる。弱い部分を的確にとらえられたあかねの身体がほんのりと色づいてきたことも見逃さない。
「んっ……やっ……だめです」
胸にまわす腕に力を込め、耳元にふぅっと息を吹きかけ
「ん?何が駄目なんだい?姫は私といたくないの?」
「そんなことないけど……でもっ」
あかねは今すぐにでも友雅に飛び込んで行きたかった。
「でも、ここじゃイヤ・・・・・藤姫もいるし・・・・・それに」
「そうだね」
友雅は不意にあかねの身体を離し立ち上がると、再びあかねを抱き上げた。
「えっ?」
あかねの身体が宙に浮いている、いや友雅によって抱き上げられたのだ。
「それでは、お姫様をさらってゆくまでだ」
あかねは声を立てずに笑う友雅に抱えられたまま牛車に乗り込むことになる。
友雅はスルリと体制を整え、あかねを膝に乗せるといきなり唇を奪ってゆく。
最初は軽く、何度も何度も……そのうち友雅の舌があかねの口中を這いまわり唾液をからませながら、歯の裏側を幾度もなぞり、あかねの小さい舌を探り出し強く吸いつく。
「んっ……」
あかねの身体が熱をおびたように友雅の腕の中で紅く染まってゆく。
牛車が止まる頃には、友雅の手はすでにあかねの着物の裾を割って、その柔らかい太腿を弄っていた。
「あかね、さあ着いたよ」
友雅にしがみついたまま、あかねは牛車を降りる。
「ここは……?」
「覚えていない?あかねが一番最初に可愛い泣き声を聞かせてくれたところ」
「え?……あ!ここ、友雅さんの家だ……」
あかねは恥ずかしさで、顔を友雅の胸にうずめた。
「あいかわらず、恥ずかしがりやだね、姫は」
あかねの髪を梳きながら、うなじをするりと撫でる。その度にあかねの身体がビクンと震え、声を出す前に、既に感じていることを友雅に伝えてしまう。
中へ入ると、すぐにあかねの身体中に唇を這わせながら水干を脱がせてゆく。
その間もあかねに自分の印を刻むことを友雅は忘れない。まるで自分の所有物であるかのように、文机を背にして、座ると、自分の足の上にあかねを跨らせる。
「あかねはここが弱いのだったね」
うっすらと浮き出た鎖骨に舌を這わせ、片手で乳房を持ち上げるようにギュっと掴んだ。
「あっ……あぁっ……」
あかねが身体をよじり、両手を友雅の背にまわしてゆく。
「と・・友雅さんっ・・・・」
その声を唇で塞ぐと、あかねの背中に指を這わせ、もう片方の指で胸の蕾をさぐる。指の腹でこすると、あかねは友雅の中で甘い吐息を洩らした。
「ここがそんなにいいのかい?」
耳元で囁き、それまで背中を這っていたほうの手でも蕾をつまみあげる。
「……んっ!!……あっ……やっ、だ、だめぇ……」
「こんなに固くとがらせて、だめはないだろう?本当はどうなの・・・あかね?」
指は容赦なくあかねの蕾を執拗に責め続ける。
「あっ……あんっ……はぁっ……き、気持ち、いっ、んっ……」
「気持ちいいのかい?こんなに強く捻られても気持ちがいいのか、あかねは」
「やっ……い、いい……のっ」
「もっと気持ちよくさせてあげるよ、姫の望むままにね」
あかねの身体がむずがるように左右にゆれる、と、急に友雅の手が離れた。
「ん……はぁ……」
あかねが濡れた瞳で友雅を見つめる。
「あかね、立ってごらん・・・・・・どうした?腰が立たないかい?」
戸惑うあかねの腰を両手で持つと、自分の目の前にうっすらとした茂みがくるように立たせた。
「やっ……と、友雅さん……」
あかねの声を無視して友雅はその濡れそぼった花びらに舌を挿しこむ。そこに溢れ出る蜜を舐めとりながら、襞を一枚一枚、ねっとりとした舌でかきわけてゆく。
「あっっあっ……いやっ……んんっ」
熱く柔らかい舌で、花芯を舐め上げ、小さな花びらを甘噛みすると、あかねの声がさらに大きくなり身体を弓のように反らせては、また甘い悲鳴をあげた。
「あんっ……んっ……と、ともまさ……さ、んっ……もう、もうっ」
「ん?あかねは、もうだめなのかい」
自身の舌のかわりに、その長い指を突き入れると、あかねの蜜が友雅の手をぬらしてゆく。
「はっ……あっ、そんなにしたら……だめっ……だめ、だめっ」
あかねの中で指を少し曲げては、声のあがる部分を刺激する。
さらに指を増やし、クチュクチュと音を立てながら入り口から最奥へと突き上げた。
「やっ、いやっ……指じゃ……いやぁっ」
そんな友雅の攻めに、あかねは気をやってしまわないよう、唇を噛み締めながら必死で耐えていた。
「あかね……そんなにかみ締めてはいけない」
「あっ……んっ……でも」
「ねえ、あかねは何が欲しいの?指じゃいやなのだろう?」
「う……ん……はぁっ、いっいやぁ」
「じゃあ、言ってごらん。何が欲しいんだい?・・・言えるね」
あかねの中ではまだ友雅の指が蠢いていた。
その刺激を身体中で感じながら、あかねは恥ずかしそうに、途切れ途切れに応える。
「と、友雅さんが……」
「もっと大きな声で言って。私が、なに?」
友雅の指が奥に突きあがる。
「あっ!!んっ!友雅さんが、友雅さんがいいの……友雅さんがっ……欲しいっ」
あかねが叫ぶように答えると、友雅はあかねの頭を抱き寄せて口付けする。
「よく言えたね、あかね。私も、姫が欲しいよ、ほら・・・・こんなに姫を欲しがってる」
あかねの手をとり、自分自身に触れさせた。
「あっ……」
「これがあかねの中に入るんだよ、いいね」
友雅は寝室まで連れてゆく時間ももどかしく、自分の着物を脱ぎ、それを床に広げると、あかねを押し倒した。鮮やかな絹物の上に真白な体。
見下ろすように、優しく微笑むと、友雅はその笑みとは裏腹な力強さであかねの膝を掴み、思い切り開かせると一気に自身を押し入れていった。
「あっ、友雅さんっ……あぁっ」
「あかねっ……とてもキツイよ」
あかねの襞が絡みついては友雅自身をキュッと包み込む。
友雅はあかねの膝を持ったまま、その足をさらに広げて、淫らな音を立てては奥へと突いた。
「あっあっ……と、友雅さん……とも、まささぁん」
感じながら自分の名前を叫ぶあかねが愛しかった。
愛しければ愛しいほど、もっと鳴かせてみたいと思うも、いつものようには相手を喜ばす余裕もなく、ただ己の思うがままに、あかねの中に突き立てることしかできない。
部屋の中には、あかねの友雅を呼ぶ声と、友雅が入る度にクチュッ、クチュッというあかねの音だけが響いている。
――あかね……もっと乱れておくれ
私の愛しい人……もっと、もっと私を感じておくれ---
「あんっ、あっ……友雅さんっ……やっ」
あかねの足が反り返り、爪が友雅の背中に食い込んだ。
友雅はその痛みさえ甘美だと、あかねをきつく抱きしめる。
「あっっだめっ、だめっ……ほんとに……ああっ」
「もういきたいかい?」
あかねは喘ぎながら、頭をふった。
「一緒にいこう。私も、もう……」
友雅の動きが一層激しくなる、あかねを突き上げ自分の腕の中で幾度も揺らす。
「あっあっ……だめっ……いっいくっいくっ……いっちゃうよォ」
「いいよ、いってごらん、あかね」
友雅の腕に力がこもる。あかねの身体が一瞬大きく反り、友雅自身を強く締め付けた。そして、すぐに小刻みに震えて、あかねは友雅の腕に抱かれて落ちていった。
友雅もまた、あかねに包み込まれて同時に果てていた。
愛し合った後はいつも、あかねは友雅の胸に顔を押し付ける。
今日も同じように紅い顔を友雅の胸にうずめていた。
――私の姫は顔を見られるのが恥ずかしいらしいね
微かに寝息をたてはじめたあかねを抱いて、寝室へと連れてゆく。
「んっ……」
途中、あかねは目をあけるが「いいから、眠っておいで」と、額に友雅の唇を受けながら、また眠りに落ちる。
友雅はあかねを腕に抱いたまま横になると、初めてあかねを抱いた日のことを思い出していた。
――あの日……神子殿は「遊びでもいい」と言ったね。
あなたのことを少女だとばかり思っていたから、正直驚いたよ。
確かに、私もそれでいいと、遊びでいいと思った。そう、慣れていたからね。
だが、いつからだろうか、遊びでは終わらなくなったのは。
あかね……名を口にするたびに狂おしいほどに私の胸は熱く乱れる。そうさ、遊びではいられなくなったのは私のほうだ……この私がね……
あかね、あなたが私をそうさせた。
それでも、あなたを求めた後は、いつも胸が痛むよ。
あなたのその寝顔をいつまでも見ていたい……私だけのものにしたい。
でも、いつの日か、あなたは元の世界に戻る日が来る。それなのに、こんなことをしてはいけないのではないかと……これでも自分を責めているのだよ。
あかね……愛しい人。
わかっている、わかってはいるよ、私も……
私たちの未来が幕を閉じる時が来ることを。
それでも……
それでも今は
刹那なきみを……抱いていたい。
この胸に。
決して永遠にはなりえない……刹那なきみを……
そして友雅はきつく瞳を閉じた。
| |
| [了 / 刹那な君を] |
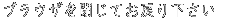
|
|