|
キラキラキラと星が瞬く間だけ、あなたの隣で躍らせて。
作り物の世界でも、夢でなければそれでいいの。
「こんにちは〜」
そう言いながら有川家に入ろうとした望美は、あれ?と首をかしげた。
「おかしいなぁ、誰もいないのかな?」
いつもならば簡単に開く有川家の玄関に、どういうわけか今日はしっかりと鍵がかかっている。
めずらしい……
でも、本当はそれが普通なんだよね。
望美はそんなことを思いながら、人差し指でインターホンのボタンを押した。
――ピンポーン
聞きなれない音が鳴る。
(あれ?もしかしたら初めてかも)
幼い頃から、まるで自分の家のように出入りしていたお隣さん。その有川家の呼び鈴を望美はこれまでに鳴らした記憶がなかった。
「っていうか、昔はこんなのついてなかったよね」
押したボタンの隣の、赤い色の小さなランプを見ながら、望美がそんなことを考えていると、
『名を名乗れ』
予想もしない声がスピーカーから聞こえてきたものだから、望美は目を丸くして驚いた。
なっ、なに今の?
『用事がある者なら、はじめに名を名乗ってもらおう』
どうやら、応対をしているのは九郎のようだ。らしいといえば、これ以上彼らしい言葉もないが、それにしても、名を名乗れと言われても。
「九郎さんですか?私です、望美です!」
九郎と望美は恋仲である……と、望美は思っている。恋人らしいことは何ひとつしてないじゃないか、と言われれば、すぐに返事に困ってしまうのが実際のところだが、こういうのは気持ちが大事なのよね、と望美は思うようにしていた。
図らずも、その想い人の声を、こんな形で耳にすることができるなんて。普段、直接お喋りするのもいいけれど、こういうのって何だか当たりくじを引いたような気がして、望美は声をはずませた。
「九郎さんですよね?こんにちは!」
そう言うと、スピーカーの奥で篭ったような咳払いの音が聞こえ、あれ?と思う間もなく
『姓は何という』
またしても、九郎の厳しい声が聞こえてきた。
「やだなあ、何言ってるんですか。早く開けてくださいよお」
『断る』
まさしく一刀両断。即答され、望美があっけにとられている間に、点灯していた赤いランプも消えた。消える寸前に、ガチャガチャと派手な音がしていたのは、九郎が受話器を戻すのに手間取ったのだろう。
その九郎とドアを挟んで対峙している望美。
「え?」
一瞬、意味がわからない様子で、ぽかんとしていたが、一方的に切られたことに気が付くと、思わず大声で叫んでいた。
「なっ、なによ!九郎さんったら……いったい何なのよっ、もうっ!開けろー!」
「もう、なんですぐに開けてくれなかったんですかぁ」
「馬鹿かお前は。そんなに簡単に開けてしまって、もし不審者だったらどうする。譲にも将臣にも二度と顔向けできなくなるじゃないか」
「だって、私だってことわかってたんでしょう?だったら……」
恨めしそうに九郎を見上げる。
「念には念をいれんとな」
留守を頼まれた意味がないだろう、と九郎は少し得意気な顔で言った。
―― とかなんとか言っちゃってさ。あれは絶対に意地悪だよ。
有川家にあるのは、テレビドアホンだから、声だけでなくドアの前に立っている望美の姿も確認できたはずだ。
だから絶対にわかっているはず。それなのに、何度も押し問答を繰り返し、しまいには合言葉用の和歌まで持ち出してきたときには望美は呆れてしまった。
とはいえ、無事に(?)ドアを開けてもらえたからこそ、こうして話もできるのだが。将臣たちに知られたらそれこそ大笑いされるだろう。
それに……あれが、本当に責任感からの行動だったら、こうして望美と一緒に街に出たりなどしないのだ。
ドアを境に押し問答を続けた二人は、揃ってそのドアを開け、今、地元を少し離れた大きなデパートのある街中へと出かけていた。
もともとそういう約束があったわけじゃない。きっかけは、九郎が食べていたカップラーメンだ。
将臣に教わって以来、いたく気に入ったらしい。
さっきも、朝食はしっかり食べたのに、小腹が減ってな、と一人ズルズルと麺をすすっていた。
それを見て美味しそう、そう思う望美もついさっき朝食を食べたばかり。じっと自分を見つめる瞳に、九郎がふっと顔をあげた。
「望美も食うか?」
「ううん、今はいいです」
そう言いながらも、首はしっかりと頷いており、なんだその態度は、一体どっちなんだ?と、九郎が叱るように言うものだから、売り言葉に買い言葉で、ええ食べますよ。食べたいですよ!と、望美も怒りながら台所の収納庫の扉をあける。だが、そこには。
「ねえ、九郎さん」
「なんだ」
「無いんですけど」
「何を言ってるんだ、あるだろうまだ」
「いえ、一個もありません。九郎さんいったい毎日いくつ食べてるんですか?こういうのって、非常食とか夜食とか、あとたまに食べるのはいいけど、あんまり食べないほうがいいんですよ」
けれど、この味を教えてしまったのは自分たちなのだと思うと、望美はあまり強くは言えない。どうしても歯切れの悪い口調になってしまう。
「そういうものなのか?」
「多分……ですけど、あまり毎日は……」
「それほどは……そうだ、景時じゃないのか?」
確かにそうだ。なにもカップラーメンを好むのは九郎ひとりではない。でも最後の一個を食べたのは間違いなく九郎である。自分でもそれは承知しているらしい。珍しく気弱な声で、買ってきたほうがいいだろうか?と、望美に問いかけた。
とにかくまあ、こんなやりとりがあり、だから最初はただ、カップラーメンの買い置きのために外に出たのだった。スーパーマーケットに行って、そりゃあいくつか余計な物を買ってしまうかもしれなかったけれど、電車に乗ってお出かけするという予定はなかったはずだ。
それではどうして?答えは単純。
スーパーへ向かう道すがら、通り過ぎる子供達が、口々にメリークリスマス!とはしゃいでいる声を望美が耳にしてしまっただけ。……冬休みが始まる前に立ち寄ったショッピングモールに飾られていた大きなツリーを思い出してしまっただけなのだ。
「どうかしたか?」
道の真ん中で、突然立ち止まった望美を振り返る九郎。望美はほんの少し考えるような素振りを見せたが、すぐに満面の笑みを浮かべ、九郎の腕をひっぱった。
「九郎さん、こっちです!」
「おい、こんなところで本当に売ってくれるのか?」
九郎が不安そうな顔で望美を見るが、望美は「何がですか?」と、いたって暢気に聞き返す。どうやら当初の目的、カップラーメンのことはすっかり忘れてしまっているらしい。
目の前の光景を見れば、それも無理もない。
まばゆいばかりのイルミネーション、家では到底飾ることのできない大きなクリスマスツリー。どこもかしこもクリスマス商戦に賭けているらしく、ショッピングモールの中へ一歩入れば、そこはまるで夢の国のようだった。
明日はクリスマスイブ。
ほんとは明日の方がよかったんだけどな。
ほんの少しだけ、今日がまだイブでないことを残念に思うが、明日は明日で有川家での大々的なクリスマスパティーが控えている。今日も、譲や将臣をはじめとして、八葉の皆で明日の準備に出かけたのだそうだ。そんな訳で大事な留守を守る役目を仰せつかったのが九郎だった。
その九郎も、なにやら興味深い物でも見つけたのか、さっきの心配そうな顔はどこへやら、夢中になって見入っている。
あれこれと買い物をし、食べたことがないという九郎にソフトクリームをご馳走したりしていると、気が付けばもう夕食の時間だった。
「疲れたな」
「そうですね。私もちょっと」
セルフサービスのドリンクを片手に、広場にあるベンチに二人で座った。
「今、何時だ?」
「ええと」
腕時計を見ると、もうすぐ六時といったところだった。空は既に真っ暗で、遠くに星が輝いている。
「明日も晴れますね」
「ああ、だが、それにしても星が少ないんだな」
「お腹空きましたね」
「お前っ」
「なんですか?」
「俺の話を聞いてなかったのか?」
掴みかからん勢いで九郎が望美を見た。
「え?聞いてましたよ。ほんとに星少ないですよね。でもお腹空きましたよね」
以前の望美ならいざ知らず、今や九郎たちの時代の空も知っている。だからこそ、九郎の言うこともよくわかるのだ。けれど、それはそれ、これはこれ。何しろ昼ご飯も食べていない。
「まったく。飯のことしか考えないのか」
「そういうわけじゃないですけど、朝食べたきりだから、もうペコペコなんです」
「そ、そうか。だが……」
財布の中身をちらりと見て、九郎は肩を落とした。さきほど立ち寄った店で、ほぼ使い果たしてしまったようだ。とてもじゃないが、外食など。周囲にあるファーストフードですら怪しい。
「私もお金使っちゃったんです」
つい浮かれてしまった。それに、九郎に似合いそうなマフラーを見つけ、クリスマスプレゼントにと、奮発してしまったのだ。
「そうか、二人合わせても無理か。だが乗り物に乗る金は残しておかないとならないしな」
そう言って、すまなそうな顔をする。
「いいんですよ。きっと私達だけ食べて帰った方がみんな怒りますって。何も言ってきてないし。さあ、そろそろ帰りましょう」
さて、と勢いよく立ち上がった望美だが、空腹のためか、疲れが出たのか、その途端足がもつれるようにふらついてしまった。
「うわっ!」
「馬鹿っ、お前何やってんだ」
グラっときた瞬間に、その身体を九郎が抱きとめた。頭を胸に抱え込むようにして、大丈夫か?と聞くと、望美が小さく頷いた。
「あ……」
「どうした?どこか痛いのか?」
「そうじゃなくて、この曲……六時になったみたいですね」
「曲?」
クリスマスの期間中、決まった時間になるとアレンジされたクリスマスソングが流れるのは、このモールの恒例だ。選曲がロマンチックなこともあり、恋人達はみな時間を合わせてここへ来るのだ。特に夜は、いっそう良いムードになる。
「私、この曲好きなんですよー!」
その声に、「なんだ、もう大丈夫らしいな」と九郎は抱きしめていた身体を離そうとした。が、望美は動かない。ふと見れば、神妙な顔つきで九郎の腕をぎゅっと掴んでいる。離さないでくれと九郎に頼む。
「お願いです。この曲が終わるまででいいですから、今だけでいいですから、こうさせてください」
「の、望美、お前っ、……」
次の句が出てこなかった。
なんなんだいったい!人が心配してやれば!さっさと行くぞ!いくつもの言葉が頭の中を駆け巡る。けれど、どれひとつ言葉にはならなかった。九郎にしてみても望美は誰より恋しい女。好きな女に抱きつかれて嬉しくない男などこの世に存在しない。だが、いつも自分が源九郎義経であるということが、九郎をなかなか素直にさせてはくれなかった。二言目には、武士たるものが、男児たるものが、そう口にしていなければ自分を見失いそうになるのだ。
「……あとどのくらいで終わるんだ?」
「もう、あと三分くらいです」
「おい、まだか?いい加減離れたらどうだ?」
「嫌です」
これまでに、三分間がこれほど長いと感じた時があっただろうか。望美は曲が終わるまで三分だと言う。だが一向に曲は終わらない。不思議だ。
「ほんとにお前は。恥ずかしい奴だな」
「恥ずかしい奴でいいです」
まったく!人前で抱き合うなど恥ずかしい。……恥ずかしいことに違わないのだが、何故か九郎は望美の背中に手をまわしていた。
結局、有川家に帰ったのは九時をまわってしまった。
予算の関係で外食をあきらめた空腹のお腹の虫は遠慮なく鳴いている。そのおかげか、本来の目的を思い出した二人は途中のコンビニでカップラーメンを買い込んだ。皆の喜ぶ顔が見れると思って勢いよく扉を開け、「ただいまー!」と言った二人を待っていたのは、二人の予想に反してムスっとした集団だった。
「九郎、キミは、鍵を預かるという意味を知っていますか?」
口火を切ったのは弁慶だ。鍵の無い弁慶たちは有川兄弟が帰宅するまで、寒い中、ずっと外で待っていたらしい。これには二人とも一言の言い訳もできず、ただひらすら頭を下げた。だが、お腹の虫はそうはいかない。
「あの、夕飯は……」
その続きは言わせてもらえなかった。ジロリと睨まれ、「それでも食えば?」とヒノエが笑う。
手提げの中身は全部カップラーメン。お湯を沸かして三分間。かくして二人は、空腹が何よりのご馳走だと知るのだった。
|
――fin
|
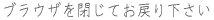
|
|
|

