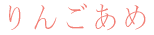 |
|
赤くて、丸くて、可愛くて・・・・・ 「あっ、見て見て」 里緒の指差す方角は、夏祭りの出店の中でも、とりわけ赤い色を放っていた。 ---あ・・・・ 「里緒」 涼は里緒の言葉をきっぱりと切った。 だが涼の手は里緒に引かれ、目の前には既に透明なパラフィンに包まれた真っ赤なりんご飴がいくつも並んでいる。 「だーめっ」 里緒の気持ちを見透かしたように先手を打つ。 「えっ、駄目って何でよぉ。私まだ何も言ってないのに」 「じゃあどうして俺を連れてくるの?食べたいんだろりんご飴」 りんご飴と涼とを交互に見つめてから里緒はコクリと頷いた。 「だから、だーめ」 「で、でも・・・」 「里緒、確か歯医者行ってなかったっけ?りんご飴って歯によくないんだぞ」 「そうだけど、でも一個くらい大丈夫だよ」 一個くらい?呆れたように里緒を見る。一個くらいだと? 「ねえ里緒、一個で足りたことなんてあったっけ?」 そうは言いつつも、里緒が言い出したらきかないことはよく知っていて、黙ってはいるが、この場を一歩も動こうとしない足がよい例で、これはもう勝手にさせるしかないかな、と涼が思い始めた頃、たくさん並んだりんご飴の片隅に一回り小さな、まるでミニチュア版とも言うべきりんご飴があることに気付いた。 「涼兄、一個だけって約束するから、ねえいいでしょう?」 「んー。そうだな、じゃあこっちの小さなりんご飴を俺と半分ずつ。これでどう?」 「え?あ、これヒメリンゴかなぁ、可愛い」 「そう、これを半分だけ。それならOKだけど」 「うん、わかった。じゃあこれ、これがいい」 店先から、ヒメリンゴのりんご飴を一つ買うと、半分だぞと念を押しながら、里緒の口元に飴を差し出した。里緒はほんの僅かに眉をひそめながら、それでも嬉しそうにリンゴに刺さった割り箸をそっと掴んで、涼の顔をうかがいながら、小さな舌を出して飴を舐め始めた。 飴を舐めながら歩き出すと、祭りはもう終わりとばかりに出店が一斉に片付けをはじめていた。ひとつ、ふたつと堤燈の灯がおろされるごとに、祭りに来ていた人たちも一人、二人と姿を消してゆく。 だんだんと寂しくなってゆく境内で、里緒はなお嬉しそうに飴を舐めていた。 最初は遠慮がちに、おずおずと・・・だが今や、割り箸をしっかり握り締めて夢中になって食べる姿に、見ているだけで涼の口の中にも甘酸っぱい味が広がるようだった。 「約束をお忘れではないですよね?おじょーさん」 「あ!!」 「あ?・・・どうしたの?」 涼が可笑しそうに繰り返す。 「私、は、半分・・・」 里緒は自分が握り締めている飴を見つめた。 涼が同じように飴を見れば、半分どころか、透明な飴の部分はすっかり食べ終わって、中の小さなリンゴには無残にも齧られたあとだけが残っていた。 「うん、これは半分?」 「あ、あの・・・涼兄?」 「里緒、約束のことすっかり忘れてたね」 とたんに里緒が赤くなった。りんご飴のようにまあるく赤く染まった。 「ご、ごめんなさい。涼兄食べたかった?」 これでよければ、と、食べる部分などほとんどない飴を差し出しながら頭を垂れる里緒が何故か妙に可愛くて、たまらなく可愛くて、だから意地悪をしたくなる。 「なんだよこれ。ぜんぜん残ってないじゃないか」 「ごめん」 「里緒、りんご飴美味しかった?」 「うん、すごく・・・・ご、ごめんねぇ。そんなに食べたかった?」 「あーあ、食べたかったなぁ、りんご飴」 「じゃ、私買ってくるよ。おじさんまだいるみたいだし。売ってもらってくるから」 駆け出していこうとする里緒の腕を掴むと、涼は「嘘だよ」と笑った。それから掴んだ腕を引き寄せて「大丈夫」 ・・・・俺はこっちを食べるから・・・・ そう言って、里緒の唇に薄っすらと残っていた透明な蜜を舐めた。 驚いて暴れようとする里緒の両手を掴み、たいして残ってもいない飴が落ちないようにする。 目に微かに涙を湛えて自分を睨み付ける、そんな姿すら、たまらなく可愛い。 少なくはなったとはいえ、まだ人のいる境内で。 けれど、涼は我慢できずに、里緒の唇から蜜が落ちないように全部舐め取った。 「信じられない」 境内に里緒の怒鳴り声が響き、その後に小さな笑い声が落ちた。 「あ・・・・」 家に着いた里緒が洗面所で声を上げた。 「ん?どうした?」 「りんご飴食べたら真っ赤になっちゃった」 ベーっと舌を見せる里緒に、食べすぎなんだよと呆れ声をかける涼。 ---りんご飴食べたら真っ赤になっちゃった だけど本当は、りんご飴に染まったのが半分。 あとの残りは涼が染めた赤。 涼の中に甘酸っぱい味がまた広がった。 |
|
終わり お手数ですがウィンドウを閉じてお戻りください |
|